from 「Gold」
ヴィンテージ感出そうとする問題
ワイはな、ワイは現代の録音のくせに「ヴィンテージ感を出そうとしてローファイなサウンドにする」のが嫌いなんや。いや、わかるで、あの頃の音は不思議なカッコ良さがあるし、昨今のデジタルな音楽に対するカウンターパンチ的な意味でもニーズがあるんやろな。
ただや、50年代から70年代前半までくらいのあの角がない丸ーい音像が素晴らしいのは実際にその時代の音楽だからという事実も大きいと思うんや。よう考えてみいや。東京にある歴史が浅いお寺よりも京都のそれこそ千年以上前から存在しているようなお寺の方が目の前にしたときなんか安心せえへんか?ということなんよ。ワイは自分の生命よりもずっと長いことそこに存在している、という事実に圧倒されたいのよ。
音楽も同じなんや。演者はもう亡くなってしまってる。でも今ここでその当時の演奏が聴ける。音楽によって永遠の命を感じる瞬間や。その時代背景をそのまま反映しているからこそ、こもった温かいサウンドがリアルなんや。もちろん、変化球的な使い方はアリやと思うで。でも、憧れが強すぎて全編ヴィンテージサウンドにしてまうのは違うやろ。そこにリアルはないんや。
そこでエラ・フィッツジェラルドや。彼女が活躍していた時代って、基本的に「作曲家の先生と歌手」という役割分担がメインで、一つの曲をいろんな歌手が同時代に歌っていることも珍しくなかったんやな。ワイも当然全てをフォローできてるわけはないんやけど、エラのバージョンがいっちゃん好きなことが多いんや。
ジャズボーカルって結構人によってメロディを大きくアレンジできてしまうんやけど、ワイとツボが合わない歌手やと「あぁ違うんやなぁ、いっちゃんおいしいメロディ殺してしもてるで自分」ってことが多くてちょっとしたストレスになるんや。
その点エラは良い意味でワイの想像を超えた変化を加えてくるんやな。しかもクセがないんや。サラッとしてるんや。同じジャズボーカルでもサラ・ヴォーンはサラッとしてへんやん。サラやのに。クセ強いやん。エラはサラッとしとんねんなぁ。エラッとじゃなくてサラッとしとんねん。
それを強く思ったんがまあ泣く子も黙るスタンダードナンバー「Misty」やなぁ。この曲のエラヴァージョンは聴けば聴くほどすごいで。まず、メロディのアレンジが絶妙なんや。「that’s why I’m following you」の「following」の外し方とか、「On my own」の前に「ウォホホホホホーン」を加えちゃうとか(この曲、歌詞もステキなんやなぁ)。
さらにサビの高音パートで普通はグワァーっと盛り上げたくなる、というか声を張らざるをえないところをエラはサラッと軽めに歌うんやなぁ。ということは聴いてて疲れへんのや。穏やかな波に揺られているようなもんや。これが気持ちええんや。フランク・シナトラバージョン聴いてみ。声の圧が強すぎてごっつう疲れるで。
流しているだけで幸せになれる「最上級のBGM」やと思うわ。聴き手の集中を強制せずに、場の空気を作り上げる。ほんま超一流歌手やで。まあ、ワイが改めていう必要ないけどな。
当時、リスナーはどんな気持ちで聴いていたのかなぁとか想像が膨らむやろ。これはマネしてもだせない深みやで。こういう体験ができるのが本当のヴィンテージサウンドや!


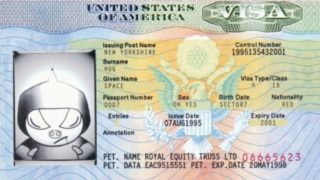

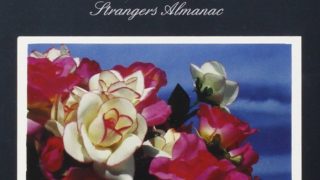
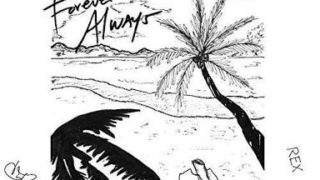


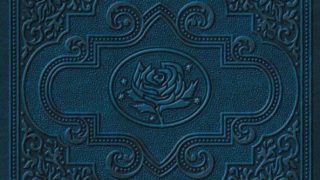
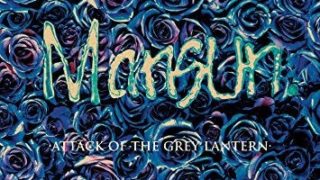
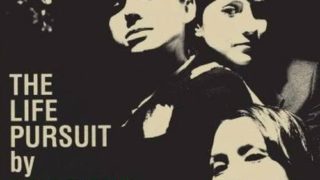

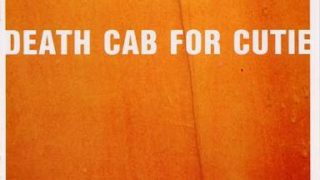
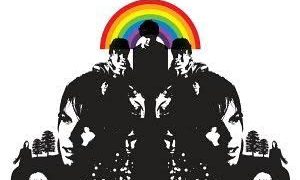





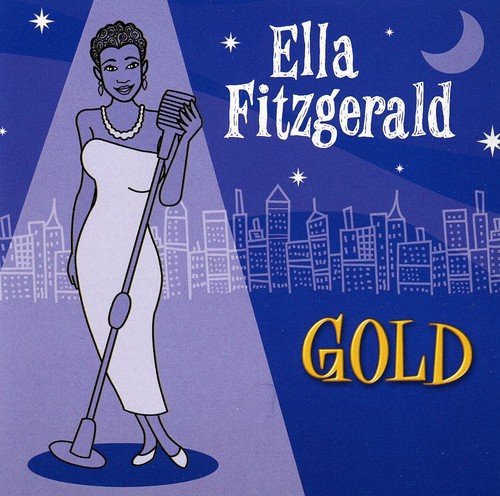


コメント