オイッス!今回は前回の(荒れた)「過大評価されているアルバム」の真逆で、「名作やのにどう考えても過小評価されてるやろ!ええ加減にせぇよ!」をテーマにお送りします。
「過小評価されている作品」って結局「オレは大好きなんだけどイマイチ売れてねぇな」という作品なんですよね。
だから洋楽痛のみなさんならばそういう作品が少なくとも10枚くらいあると思います。自分の中の作品を思い浮かべながら読んでいただけると幸いです。
これは世の中に広めたいという想いで書いています。できればこれこそ拡散に協力していただきたい。
それではジャンルめちゃくちゃでいってみましょー!
Mansun 「Kleptomania」(2004)

バンド解散後にファンの署名によりリリースされた未発表オリジナルアルバム。アウトテイク集とセットで3枚組。解散したバンドとは思えないほどに創造力が研ぎ澄まされていたことがわかる隠れた名作。「SIX」だけじゃねーんだぞ、と。
頭の名曲3連発は彼らのキャリアの中でも最高レベル。
「Getting Your Way」はアレンジも含めて最高傑作としても良いと思ってます。渦を巻くようなマンチェスター風グルーヴが気持ち良すぎ。歌メロもラップのような斬れ味と耽美な要素が同居していて、これぞマンサンの真骨頂。
続く「Slipping Away」も同系列の曲で、これを並べたのが本当に上手い。離して配置すると「アレ?なんか似てる曲あるやん」って思っちゃうところを並べることでもはや一つの曲と化しています。
「Keep Telling Myself」はポール・ドレイパーとしてソロで来日した際も演奏されて、本人もお気に入りと語っていました。
ポールの天才性を再確認できる作品。
Wilco「being there」 (1996)

3rd「Yankee Hotel Foxtrot」の影に隠れがちな2ndアルバム。アヴァンギャルドな一面もあり、スタンダードで美しいメロディあり、エレクトリック要素なし、生楽器を堪能できる、実はとても贅沢な2枚組なんですよ。
「Far, Far Away」「Red Eyed and Blue」「Hotel Arizona」「Say You Miss Me」「Sunken Treasure」などWilcoの美メロがこれでもかと堪能できる傑作。
特に「Hotel Arizona」はオトコの哀愁とドライブ感、アメリカンロックの真髄が味わえます。これを聴かないのはマジもったいない。
「Sunken Treasure」もワンリフで押していく構成で、サビで急に切なくなるし、シンプルな作りなのに世界観が完成している。一人でゆっくり散歩でもしながら聴きたい。後のLoose Furにも繋がるカオティックノイズも味わえます。
New Radicals「Maybe You’ve Been Brainwashed」 (1998)

デビューアルバム1枚を残して解散した(わたしの中で)伝説的なアーティスト。
基本的にダサいんですよね。一般的なクールさはない。ジャケットを見てもそれはわかるんすよ。でもね、彼らの音楽には芯があるんですよ。明確なアイデアが。
歌声も不器用で、細部を見ると所々ダサいアレンジとかがあるんですけど、メロディにそれを凌駕してねじ伏せるほどの説得力がある。
「You Get What You Give」は、大衆性とメッセージ性を兼ね備えたエバーグリーンで素晴らしい楽曲。歌詞を読みながら聴いたら泣いてしまうよ絶対。ちゃんとフックがあってそれがすんごい切なくて、人生に迷っている人は必聴です。
この曲だけの一発屋に思われるかもしれませんが、アルバムとしてもグッドソングの宝庫。「Gotta Stay High」の優しい歌声とメロディよ。サビの切なさなんやねん。「Flowers」もヒット性十分のアンセムやろ。大合唱するしかないやんこんなの。
フロントマンのグレッグ・アレキサンダーは幸いアーティストに曲を提供して今も世の中に名作を残してくれています。Santanaの「Game Of Love」とかAdam Levine「Lost Stars」とかね。
過小評価という言葉しか思いつかない隠れすぎた名作。
Maxwell「Now」(2001)

これねぇ、マジで聴いた回数でいけばTOP10食い込むわ。ランキングしたときに忘れとったわ!というほどにハマった1枚。わかりやすさのために陳腐な表現をさせてもらうと、オシャレR&Bの最高峰です。
音の隙間の埋め方とか、残響具合や配置も含めて音響的にもこだわり抜いてることがわかりますよ。ボーカルもバックトラックに溶け込んで本当に楽器の一部になっている。マックスウェルはそこまで考え抜いて歌ってる。全米チャートNo1にはなったけど、イマイチ評価されてないのが意味不明。
「Get to Know Ya」「Lifetime」「Changed」「W/As My Girl」の4連発だけで歴史的に価値あると思うんだけどなぁ。しかもケイト・ブッシュの神がかった名カバー「This Woman’s Work」も収録。どう考えても無視できないでしょ。
これは3rdなんだけど、その次が出るまでに8年かかってますね。そりゃあそうなりますわ。こんな完璧な作品作ったら。ちなみに4thはアコースティック路線に振り切ったこれまた名作。
Sparklehorse「Vivadixiesubmarinetransmissionplot」(1995)

ディラン御大と並びオレの心の師としていつも勇気をもらっているスパークルホースことマーク・リンカス。2010年3月6日、47歳で死去。自殺でした。
エリオット・スミス、イールズと並び、落ち込んだ時でも聴けるアーティストとして今でも聴き続けています。宅録サウンドと(変だけど)優しい歌声で寄り添ってくれる。
音はごちゃ混ぜだけど、メロディにアコースティックな弾き語り要素があるから、胸がキュンとなる(キモい)瞬間がたくさんある。「Saturdays」と「Cow」の流れは泣きそうなくらいに美しい。
こんな自由で美しい音楽は他では聴けない。ダニエル・ジョンストンくらいか。オレは死ぬまで彼の音楽をプッシュしていくつもりだぜ…ちなみに生前にリリースした4枚のアルバムは全て傑作。
My Vitriol「Finelines」 (2001)

エモーショナルシューゲイザーとでも呼ぶべき、独自のサウンドを確立した傑作1st。完全無欠のキラーチューン「Always Your Way」には大変お世話になりました。イントロのドゥロロロッていう音の塊からのキラキラギター、そして蒼い疾走感よ。
この湿り気とドライヴ感を体現したサウンドって本当に彼らの音楽でしか聴けないと思う。このリフを聴くたびに頭振りたくなるなぁ。ビジュアル系のようなチョーキングがまさにアートな「Gentle Art Of Choking」やフーファイばりの「Losing Touch」など、名曲を多数収録。なのに…全然話題に上がりませんやんか。昨年の来日公演が奇跡だわ。
ゴス好き、エモ好き、グランジ好き、ビジュアル系好き、シューゲイザー好き、ミクスチャー好き、どの方面からも受け止める器の大きさったら半端ない。
過小評価とはこのアルバムのためにある言葉だと思います。
Jamie Cullum「The Pursuit」 (2009)

ジャズとロックとポップスを融合させることに関しては彼の右に出るものはいない。彼の最高傑作「The Pursuit」はみなさん聴きましたか。
ジャズの要素もほどよく馴染ませながら、とにかくスタンダードな美しく楽しいメロディを刻み込むことに注力した作品。
「I’m All Over it」の弾けっぷりにまずトリコになりましたよ。大サビの盛り上げ方が上手いよねぇ。歌を歌うことの快感を教えてくれる。とこどころに魅せるピアノプレイもセンス良し。
「Don’t Stop the Music」ではダンディなのに激しいポップスを聴かせてくれる。これがカッコいいんだわ。サビで畳み掛けるアレンジが圧倒的迫力。他では絶対聴けない、ジェイミーにしか書けない曲ですわ。
彼の存在自体が過小評価されていると感じるね。赤ジャケのカバーアルバムが素晴らしくて、スマホが擦り切れるほど聴いたし、アレンジのセンスや歌声&ピアノの腕前は超一流です。
Judee Sill「Heart Food」 (1973)

何度か紹介しているアーティストですが、今回は是非2ndを知っていただきたい。
弾き語り中心だった大傑作1stと比べると、教会音楽のように厳かで冷たい感触の「The Kiss」や、ポップスの軽さや伸びやかな歌声が印象的な「The Soldier of the Heart」などサウンドの幅を大きく広げた作品。
超完璧主義者の彼女らしく、細部に至るまでのこだわりは健在で、より丁寧に作り込まれている。ジュディだとすぐにわかるメロディの個性も確立して、若くして亡くなったのが心から悔やまれる。
「The Donor」のコーラスの魔術的なリピートを聴く限り、明らかに新しいネクストレベルの表現が生まれようとしていたのがわかる。
作曲能力や歌声、その先が見たかったという無念さも含めてカート・コバーンに匹敵するカリスマとして推したい。
と、いうわけでぶっちゃけまだまだあるんだけど、今日のところはこれくらいにしといたるわ!ほなまた!

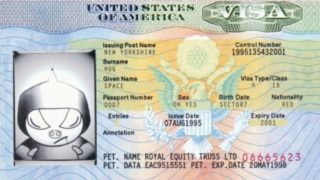



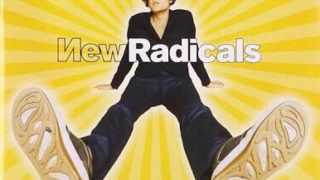

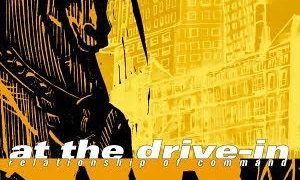

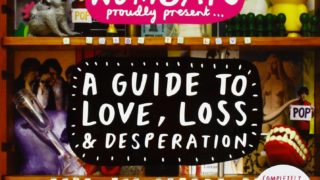


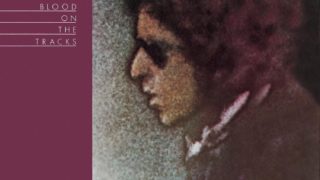




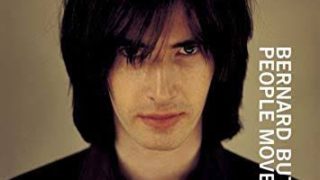
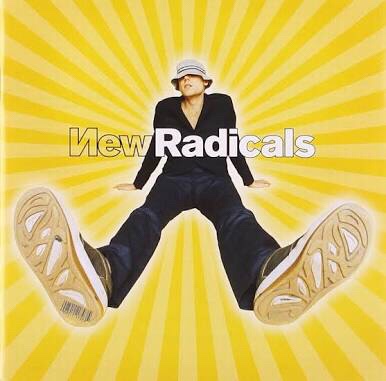

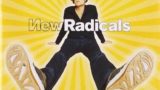





コメント